2025年7月7日・8日の両日、日本ホテル協会主催の幹部育成セミナーが京王プラザホテル(東京都新宿区)で開催されました。そのプログラムから、立教大学観光研究所特任研究員の玉井和博氏を進行役に招いて行われた座談会の様子をレポートします。
●進行役
玉井和博氏/立教大学観光研究所 特任研究員
●パネリスト
平 久氏/帝国ホテル 宿泊部ゲストリレーションズ課フロント支配人
須藤正人氏/The Okura Tokyo 宿泊部フロントサービス課課長
杉江英人氏/西武・プリンスホテルズワールドワイド セールス&マーケティング部次長
金本龍寿氏/京王プラザホテル 宿泊部ゲストリレーションズ クラブラウンジ副支配人

フルスペック型ホテルにおける市場変化
私鉄系の不動産業を22年、ホテル業界で18年、さらに大学教員として10年など、経験豊富なキャリアを持つ玉井氏が、4人のパネリストを紹介して座談会がスタートした。
話題はまず、「カテゴリー分化」について。玉井氏が不動産バブル以前の日本のホテルのカテゴリーと、不動産バブル崩壊後に起こった変化と現状について解説した。
「特に日本ホテル協会の加盟ホテル、いわゆるフルスペック型のホテルはバブル崩壊後に大変苦戦し、全体的に価格を下げてしまいました。そこへ、外資系ホテルが進出してきた一方、今までビジネスホテルと呼ばれていた宿泊特化型のホテルはその数を急激に増やしました」。さらに、現在では異業種からの参入をはじめ、さまざまなスタイルのホテルが出現していると指摘。「ホテル宿泊業は、これまでのマトリックス(分類図)が通用しないのが実情です」と、玉井氏は言う。
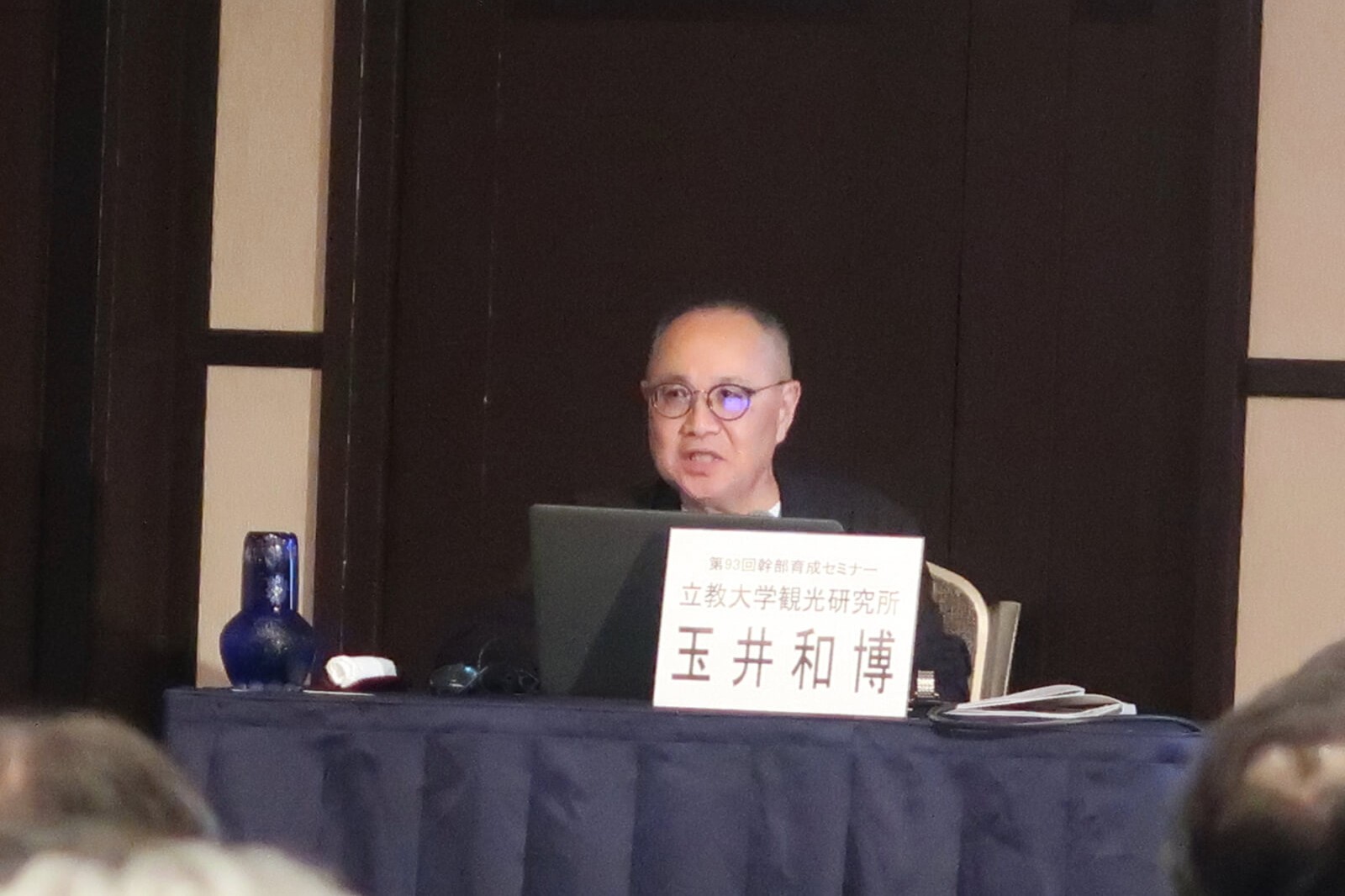
このように多極化するホテル業における「サービス提供視点」に関し、玉井氏は各パネリストに自社マーケットの変化について話を求めた。
口火を切ったのは、平氏(帝国ホテル)だ。「当ホテルでは、コロナ禍が収束し、法人契約が減少する一方で、富裕層をはじめとする観光目的の個人顧客が増加しています。それを受けて、法人契約の増加を目指す路線から脱却し、高単価な個人利用へのシフトを積極的に進めているところです」と話す。
杉江氏(プリンスホテル)は、インバウンド比率の増加について、「地域ごとに見ていくと、インバウンドの上昇率には幅がある」とした上で、「今後、どういうお客様を増やしたいのか、どういうニーズを捉えたいのかを考える上で、インバウンド比率が自然に伸びたのか、それとも自分たちが仕掛けて数字を伸ばしたのか、その分析や見極めをする必要がある」と指摘。現在、新規の会員数、会員の2回目・3回目の利用率、インバウンドのお客様の比率という3つの視点から分析に当たっているという。
一方、須藤氏によれば、The Okura Tokyoではインバウンド比率が急激に伸び、宿泊全体の約7割を占めているという。「今、必要性を感じているのは、スタッフの第2言語、第3言語への対応です。決して安くはないお金を払って宿泊されるゲストに対して、どう向き合い、どんなサービスを提供していくかがテーマの一つになっています」。
金本氏(京王プラザホテル)からは、アメリカのファミリー層の需要が増えている実情が話された。最近では、中国からのお客様よりも多いという。「個人のお客様が圧倒的に増えてきており、ホテルに求めるものが以前とは変わってきていると感じています。例えば、K-POPアイドルのライブチケットを取ってほしいなど。そうした今までにはなかった要望にどう向き合うかが、今後の課題です」。
これらの話を踏まえて、玉井氏はこう総括する。「外資系ホテルと比べて『安い』といわれる日本のホテルにおける宿泊単価アップの流れに関しては、その要因を今一度明確に整理しておくことが大切です。ただ勢いで上げてしまうと、必ず反動がきます。ポイントの一つは、自社の顧客動向におけるリピート率とリピーター率、この違いを把握することなどが重要になってくるでしょう」。

マーケットの変化に合わせたサービスの変化
次の話題は、マーケットの変化に対して、サービスのあり方がどう変わりつつあるのか。玉井氏からの問題提起に、杉江氏(プリンスホテル)は、「シームレスなサービス」と回答した。「ホテル間やホテルの近隣施設との情報共有が大切だと考えます。例えば、都内のホテルによくいらっしゃるお客様の食事やワインの好みなどの情報がグループ全体で共有されていれば、そのお客様が軽井沢のプリンスホテルに滞在されたとき、『先日お飲みいただいたワインと同じものをご用意いたしましょうか』と提案することができます」。
あるいは、ゴルフ場でホールインワンされたという情報が共有されていれば、宿泊のチェックインのときに「おめでとうございます!」とお祝いの言葉をかけることも可能になる。情報共有による個人に寄り添う接客こそが、今後のキーワードになると考えている。
The Okura Tokyoでもグループ全体の情報共有、横のつながりを意識しつつ、接客現場での細かな心遣いを忘れない。お客様への記念品サービスはその一例だ。「毎日、総支配人が宿泊リストをチェックして、誕生日や結婚記念日、ハネムーンなどのお客様には、花束やワイン、フルーツなどを事前にセットし、メッセージカードを置くようにしています」(須藤氏)。
一方、京王プラザホテルではハードとソフトの両面から新しい取り組みを始めている。「ハード面について、47階の宴会場をすべて宿泊付帯施設にしました。宿泊されるお客様が使える特典のラウンジスペースというイメージです。飲み物を提供したり、お子様が遊べるキッズスペースを用意しました」と金本氏。ソフト面では、お客様に対してこれまで以上に関心を寄せよう、という取り組みを実施。お客様の名前で声がけをしたり、お子様が持っているキャラクターグッズを話題にしたり、自然に生まれる会話を重視したサービスを提供しているという。
平氏(帝国ホテル)も同様に、「会話の中で、例えば『プロポーズ』というキーワードが出てきたら、チェックアウトのときに『おめでとうございます』とお声がけして、記念品を差し上げたり、ロビー中央の花壇の前で写真を撮り、写真立てに入れてお渡ししたりしています」と話す。
AIの活用についてもパネリストの意見は一致。テクノロジーを活用したサービスと、人的サービスをいかに融合していくかという視点から、次のような意見が出された。
- AIによるマーケティング的なデータ分析と人的な視点の組み合わせが必要。
- デジタルツールで事務仕事の負担を減らし、その時間をお客様へのサービスに還元する。
- お客様からの苦情のメールにAIを使って回答すると、決まり文句のようになってしまうので注意が必要。
こうした意見を踏まえて玉井氏は、多様化するマーケットの中で、必ずしもデータ分析ばかりが正しいとはいえない時代になったと指摘。「正しい/間違っている」ではなく、「好き/嫌い」の世界に入ってきており、情緒的な付加価値の再認識が重要だと締めくくった。
若手社員育成の課題と外国人従業員について
若手社員の離職率の高さに悩むホテルも多い中、管理職はどのように若手スタッフと向き合い、育てていくべきか。座談会の第2セッションでは「若手社員育成と外国人従業員への対応とポイント」をテーマに、引き続き議論が交わされた。以下、主なポイントを抜粋する。
杉江氏は、若いスタッフの目標や夢を応援する制度を整える必要について指摘。プリンスホテルでは、「将来はGMになりたい」「総料理長になりたい」などと大きな夢を持つ若手スタッフのために、飛び級制度をつくったり、海外で働きたい人のためにグローバル研修を整えたり、さまざまに取り組んでいるという。
メンター制度の効果について語ったのは須藤氏(The Okura Tokyo)。新入社員に対し、3~7年目の先輩社員が定期的に面談を行うという取り組みだ。「メンターは、あえて同じセクションではない人を選んでいます。新人は直属の上司や先輩ではないほうが話しやすく、離職者が減るなど一定の効果が上がっています」。
このほか、若手スタッフ育成については次のような意見があった。
- 働く環境は非常によくなっているが、働く意欲は下がっているように感じる。不満というより、不安が大きいからではないか。
- 管理職自身がプライベートも仕事も充実していないと、若手の考え方もよい方向に向いていかない。
- アンケートやヒアリングなどを通して、若い人の不満・不安を知ることが大切。
また、外国人スタッフの雇用に関しては、玉井氏から、日本人と同等の待遇・就業時間、人権の尊重といったルールを守ることはもちろん、そうした取り組みを行っていることを積極的に発信していくことが大切との指摘があった。また、パネリストからは、「外国人スタッフと日本人の、特に高齢のお客様との間でうまくコミュニケーションが取れないケースがあり、教育研修が重要」などの声が上がっていた。
最後に玉井氏は、H・ミンツバーグ教授の「日本はバランスの取れた社会、米英とは違う。MBAでは科学的根拠は得られるが、経験は得られない」という言葉でセッションを締めくくった。
「宿泊」をテーマに行われた今回の幹部育成セミナー。座談会ではそのテーマを超えて、さまざまな観点からホテルの置かれた現状について意見が交わされた。3時間におよぶセッションは会場を大いに刺激し、長さを感じさせないものだった。
構成・文/ひだいますみ
(2025 7/8/9 Vol. 752)
